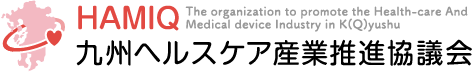研究・開発につながる調査統計データや研究情報に関するニュースを配信します。
情報提供:日本医療・健康情報研究所
-
2023.11.02医療・健康医療費の6割を占める高額医療費 メタボ予防の重要性が浮き彫りに 高血圧・糖尿病・脂質異常症を併発したメタボが32%協会けんぽの高額医療費集団169万人超の健診・レセプトデータを解析した調査で、医療費が上位10%の集団では、95%超が、2つ以上の慢性疾患が併存する「マルチモビディティ」であることが明らかになった。 高血圧・糖尿病・脂質異常症を同時に併発したメタボリックシンドロームが、全体の31.8%を占めており、医療費でも28.6…
続きを読む
-
2023.11.02医療・健康10分間の軽い運動で高齢者の記憶力が向上 運動習慣のない人も安全に取り組みる運動プログラムを開発 筑波大学など高齢者が軽い運動を10分間行うと、記憶力が即時的に向上することを、流通経済大学や筑波大学などが明らかにした。 運動には、記憶力を含む認知機能を維持させ、向上する効果があり、認知症予防策としても注目されている。加齢による「もの忘れ」の原因のひとつに、脳の広範囲の神経活動を調節する覚醒機構の低下があるとみられている。 …
続きを読む
-
2023.10.03医療・健康ウォーキングの歩数を8000歩に増やして肥満や糖尿病に対策 横浜市「ウォーキングポイント事業」の成果を発表1日に1万歩以上歩いている人は、糖尿病の発症リスクが62%、重症化リスクが67%低いことが、横浜市が実施している「ウォーキングポイント事業」で明らかになった。「1日の平均歩数が8,000歩を超えるあたりから、2型糖尿病の発症率と重症化率に差が出てきました。現状の歩数よりも、1,000~2,000歩を多く歩くようにすると…
続きを読む
-
2023.10.03医療・健康日本人は「睡眠不足」 良い睡眠はメンタルヘルスも高める 快眠に必要な2つのこととは?心身の健康を保つために、質の高い十分な睡眠をとることが必要だ。日本は先進国のなかで、睡眠時間がもっとも少ない。「日中に眠気を感じる」「睡眠全体の質に満足できない」「睡眠時間が足りない」と感じている人も多い。質の高い十分な睡眠をとると、うつ病や不安に対する回復力を高まり、メンタルヘルスが高まることが分かった。睡眠を改善す…
続きを読む
-
2023.09.04医療・健康【がん予防の経済効果】 がんのリスク要因を減らして1兆円超の経済的負担を軽減 生活スタイルや環境の改善が重要国立がん研究センターなどは、日本人のがんによる経済的負担を明らかにした。生活スタイルや環境を改善することで予防が可能ながんの経済的負担も推計した。がん予防により軽減できる経済的負担は、1兆240億円(男性 6,738億円、女性 3,502億円)に上ることが明らかになった。予防可能ながんの経済的負担は、男女ともに胃がんが…
続きを読む
-
2023.09.04医療・健康肥満やメタボが「腰痛」を引き起こす コロナ禍でさらに増加 「腰痛」を改善する運動は?世界の成人のほとんどが、生涯を通じて腰痛を一度は経験しており、半数は首の痛みも経験している。コロナ禍で腰痛に悩まされる人はさらに増えた。在宅ワークなどで長時間座り続けることが増えたり、運動量が減り、腰回りの筋力が低下していることや、ストレスや不安なども影響している。腰痛を予防・改善するために、運動を習慣として行うことが…
続きを読む
-
2023.08.01医療・健康介護・福祉聴力が低下した高齢者が孤独・要介護に 高齢者の孤独・孤立対策では難聴ケアも必要聴力が低下している高齢者は、そうでない高齢者に比べ、孤独になりやすく、要介護状態になる割合が高いことが、国立長寿医療研究センターの調査で明らかになった。難聴の重症度が高いことに加えて、・男性 ・教育年数が少ない ・現在は仕事をしていない ・1人暮らし ・運動習慣がない ・うつ傾向がある、といった特徴のある人は、孤独を感…
続きを読む
-
2023.08.01医療・健康食事の多様性が高い人は認知症リスクが低下 さまざまな食品を食べることが認知症予防につながる食事の多様性が高い人は、認知症の発症が少ないことが、4万人近くの日本人を調査した研究で明らかになった。認知症の発症リスクを少しでも低下させるために、さまざまな食品を食べることや、多様性の高い食事をとる食行動が効果的である可能性がある。認知症は加齢ととともに発症率が高くなり、日本では後期高齢者の増加にともない、認知症有病…
続きを読む
-
2023.07.04医療・健康職場のストレスを早期発見 従業員のキーボードやマウスの操作からストレスを判定 職場の環境改善につなげる企業などの従業員が、パソコンのキーボードやマウスのどう操作しているかをみるだけで、職場のストレスを判定できるという研究を、スイスのチューリッヒ工科大学が発表した。慢性的なストレスを早期に発見し、職場の環境改善などの対策につなげられるようにすれば、働く人のウェルビーイングの向上につながるとしている。
続きを読む
-
2023.07.04医療・健康肥満やメタボのある人はアルコールの飲みすぎにご注意 少し飲みすぎただけで肝臓へのダメージは大きい肥満やメタボのある人が、アルコールの飲みすぎていると、肝臓へのダメージが劇的に大きくなることが、新たな研究で明らかになった。「たまに飲みすぎる程度であれば良いのですが、大量にお酒を飲むのを習慣にしていると、進行性肝疾患のリスクが2倍以上に上昇することが示されました」と、研究者は述べている。350mLの缶ビールを1日に1…
続きを読む