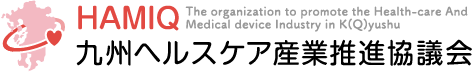研究・開発につながる調査統計データや研究情報に関するニュースを配信します。
情報提供:日本医療・健康情報研究所
-
2024.07.01NEW医療・健康メンタルヘルスを改善する効果的な方法とは?手軽に取り組める3つのストレス解消法で心と体をケアストレスの多い現代社会では、うつは「心の風邪」と言えるほど、誰もがおちいりやすい状態だ。ストレスによるうつの状態が続くと、体重が増加し肥満になりやすくなるという報告がある。メンタルヘルスと体重のあいだに関連があり、相互に潜在的に影響をおよぼしあっている。すでに過体重や肥満のある人では、うつなどのメンタルヘルスの悪化が、…
続きを読む
-
2024.07.01NEW医療・健康労働者の問題飲酒を調査!「週3回以上」「1回2合以上」の飲酒は危険信号 男女でどんな違いが?男女ともに、週に3回以上の飲酒をする人や、1回に2合以上の大量飲酒をする人は、その後に「問題飲酒」が発生しやすいことが、富山大学が1,535人の地方公務員を5年間追跡した調査で明らかになった。男性では、職位が低い人や交替勤務がある人に、女性では、仕事のパフォーマンスに関する自己評価が低い人に、問題飲酒が発生しやすいこと…
続きを読む
-
2024.06.03医療・健康高齢者の「機能的能力」を高めるために何が必要?WHOが提唱する「ヘルシーエイジング」に必要な3つの因子とは世界保健機関(WHO)は、高齢者の「ヘルシーエイジング」を示すための指標として「機能的能力」を提唱している。「高齢者の多くは、病気などの健康問題を1つ以上抱えて生きています。しかし、そうした問題を適切に管理できていれば、健康に対する深刻な影響を最小限に抑えることができます」としている。京都大学はこのほど、高齢者の「機能…
続きを読む
-
2024.06.03医療・健康猛暑は「良い睡眠」で対策!睡眠不足は高血圧リスクを上昇させる 暑い夏の夜でもぐっすり眠る3つの方法気候変動にともなう気温の上昇は、多くの人の健康に影響している。気温上昇は多くの人の睡眠にも悪影響をもたらしていることが明らかになった。十分な睡眠をとれていない人は、2型糖尿病のリスクが高いことも分かった。睡眠不足が慢性化すると、食事を健康的にするだけでは糖尿病リスクを下げられないという。睡眠を改善するために3つの方法が…
続きを読む
-
2024.05.02医療・健康職場や家庭で怒りを爆発させても得はない 怒りを効果的に抑える2つの方法 「アンガーマネジメント」のすすめ"職場や家庭で社会生活をおくるうえで、怒りの感情をコントロールするスキルや心理トレーニングである「アンガーマネジメント」は大切だ。怒りをあらわすことに得はなく、とくに職場では地位を下げることにつながりやすいことが明らかになった。深呼吸、リラクゼーション、マインドフルネス、瞑想、スローヨガ、筋肉の弛緩などが、怒りを抑える…
続きを読む
-
2024.05.02医療・健康塩分のとりすぎが高血圧や肥満の原因に 代替塩を使うと高血圧リスクは40%減少 日本人の減塩は優先課題塩分のとりすぎは高血圧に大きく影響し、肥満とも深く関連していることが、明らかになった。日本人はとくに食塩摂取量が多く、減塩は優先して取り組むべき課題になっている。そこで減塩の新しい考え方として、「かるしお」が提唱されている。減塩を啓発するために「かるしお認定制度」も推進。食塩を代替塩に置き換えると、高血圧リスクは40%…
続きを読む
-
2024.04.02医療・健康禁煙後の体重増加はどうすれば防げる? 禁煙後に太ってもメリットは大きい 健康的な生活により寿命を7年延長禁煙後に体重が増えるのを気にして、禁煙をためらっている人は多い。しかし、喫煙を続けていると、とくに内臓脂肪が増えやすくなり、長期的にみるとやはり、禁煙に取り組むことで得られるメリットは大きいことが明らかになった。禁煙に取り組み、健康的な体重を維持し、アルコールの飲みすぎを減らすことで、寿命を最大で7年延長できることも示…
続きを読む
-
2024.04.02医療・健康地域メタボリックシンドロームの新しい診断基準を提案 特定健診などの56万⼈のビッグデータを解析(新潟⼤学)新潟⼤学は、メタボリックシンドロームの診断基準の新たな修正案を作成したと発表した。ウエスト周囲径(WC)の基準値を、現行の「男性 85cm、⼥性 90cm」から「男性 83cm、⼥性 77cm」に変更し、さらには、従来のメタボ診断で必須項⽬とされているWCを、必須項⽬にしなくても、⼼⾎管疾患の⾼リスク者のスクリーニング…
続きを読む
-
2024.03.01医療・健康フレイルとうつ症状を併存すると死亡リスクが上昇 地域住民を対象にした調査で明らかに医療経済研究機構(東京都港区)と東京大学高齢社会総合研究機構(東京都文京区)はこのほど、フレイルとうつ病の併存と死亡リスクとの関連に関する研究結果を公表した。「フレイルとうつ症状のいずれもない集団」に比べ、「うつ集団が併存したフレイルの集団」は死亡リスクが約4.3倍高いことなどが分かった。
続きを読む
-
2024.03.01医療・健康就寝時間を遅らせる癖があると睡眠が悪化 就寝を先延ばしにする習慣を測定するスケールを開発 保健指導にも活用就寝時間を先延ばしにして、眠りにつくのが遅くなると、睡眠不足などにつながり、睡眠が低下する原因になる。国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は、就寝時間を遅くする習慣や癖を測定するスケール(BPS)の日本語版を開発し、睡眠習慣を判定するのに有用であることを確かめた。このスケートは、同センターのサイトでダウンロードで…
続きを読む